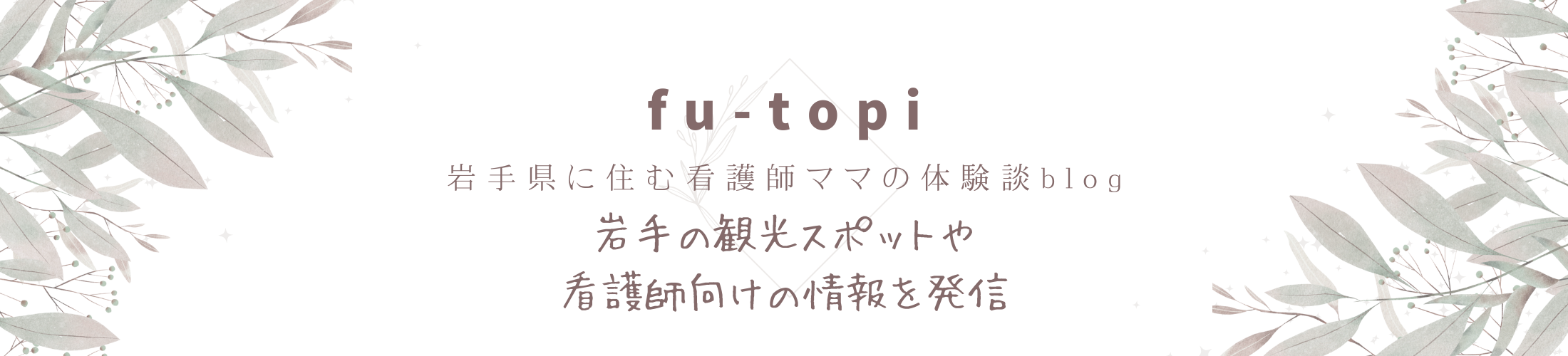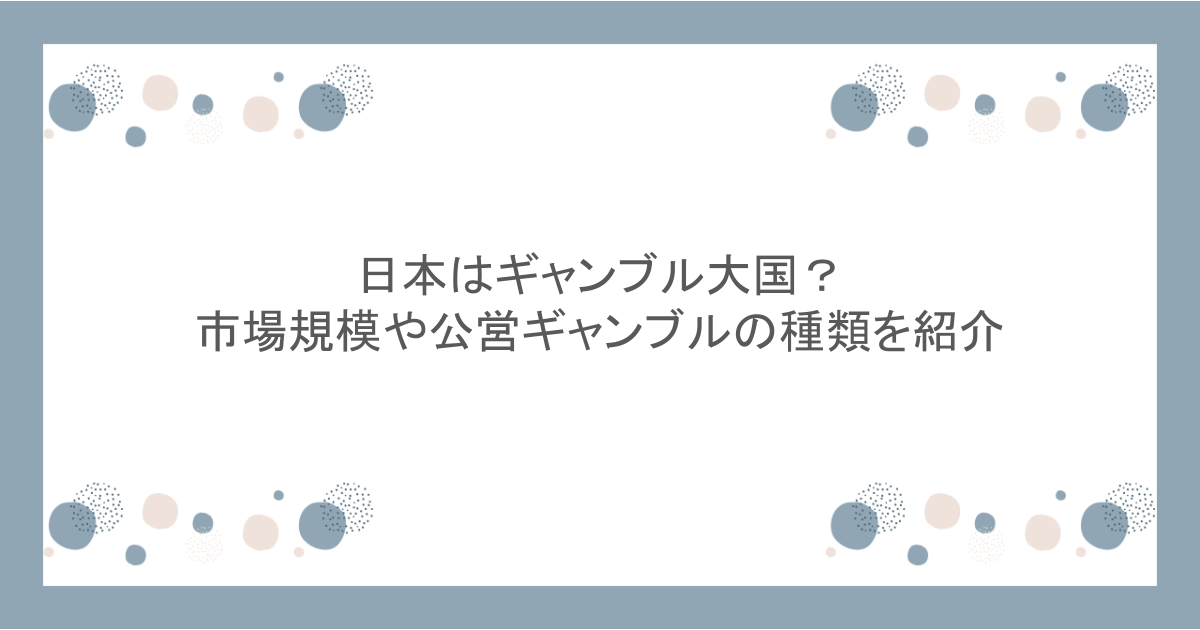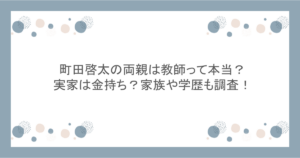日本は世界一のギャンブル大国、というフレーズを一度は耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか?世界の全ての国のギャンブル市場を把握する正確な統計は存在しないにも関わらず、この事実的な要素は私たちにも広く知れ渡っています。
身近な人や友人にもこれらの娯楽を休日の楽しみとしている人も多く、最近ではおすすめオンラインカジノの徹底比較サイトで様々なオンラインカジノと出会うこともできるようになりました。
今回は、日本のギャンブル市場について、その市場規模や公営ギャンブルの種類に焦点を当て、紹介していきたいと思います。
日本におけるギャンブルの定義
日本では、公式にギャンブルと認められているのは公営5競技と公営くじのみです。ですが宝くじやパチンコについても、あまり詳しくない人からすれば同じようにギャンブルと言えるでしょう。これらの非公式なギャンブルについては、「ギャンブル型レジャー」と呼ばれ、
パチンコは法律上、メダルゲームと称されていますが実態はギャンブル、という矛盾を抱えています。巷では日本の3大ギャンブルはパチンコ、宝くじ、そして公営5競技と言われており、広く浸透していることが分かりますよね。
今回は日本がギャンブル大国と言われる所以やその市場規模についてのリアルをみていきたいため、公営ギャンブル以外にも事実上ギャンブルと言われるものについても合わせ、まずはその市場規模を見ていきたいと思います。
市場規模
2023年の市場規模データは、パチンコが約 15,7000億円、宝くじが8,000億円前後、公営5競技が合計で約8兆3,000億円。これらを合計すると約24兆8,000億円にも上ります。これは同年の日本の余暇市場全体の約35%を占め、日本のGDP全体の4〜5パーセントに相当し、他の日本の産業と比較しても市場規模はかなり大きいです。
最近ではこれらの他にもオンラインカジノの人気も高まり、統計に反映されていない水面下の数字も含めるとやはりその市場規模は世界最大級と言っても過言ではないでしょう。
公営ギャンブルとは?
先ほど登場した公営5競技とは、公営ギャンブルとして認定されている5競技のことで、公的機関が賭博(ギャンブル)として開催するスポーツの総称です。また公営ギャンブルとして競技以外にもスポーツ振興くじなども認定されています。
なぜ公営ギャンブルは合法なの?
公営ギャンブルを開催しているのは国や自治体などの公共機関であり、それらの公的組織への経済的な貢献が期待できるためです。
後ほど競技ごとに詳しく解説しますが、例えば経済水産省は競輪とオートレースを主催しており、産業の発展と福祉事業を目的としています。
次項にて公営ギャンブルの主催組織と競技や種類の一覧を見ていきましょう。
公営ギャンブルの主催組織と目的の一覧
以下の通り、公営のギャンブルは全て目的を掲げ、国や自治体が統括しています。
| 管轄組織 | 目的 | |
| 中央競馬 | 農林水産省 | 畜産振興・福祉事業 |
| 地方競馬 | 農林水産省 | 畜産振興・福祉事業 |
| 競輪 | 経済産業省 | 産業の発展・福祉事業 |
| 競艇 | 国土交通省 | 船舶の発展・社会事業 |
| オートレース | 経済産業省 | 産業の発展・福祉事業 |
| スポーツ振興くじ(Toto) | 文部科学省 | スポーツの振興 |
赤字の続く公営ギャンブル
日本がギャンブル大国と言われる一方で、実はこれらの公営ギャンブルのほとんどが不況に苦しんでいます。公営ギャンブルとして設立された当初は人気のあった競技も次第に、倫理的観点により国民からの反対の声などが多く出るようになり、一時は新規の競技場が設立されなくなりました。時代が進むにつれ娯楽の多様化なども拍車をかけ、収益は悪化の一方をたどります。
現在では競馬人気の復興に伴い一定の収益はあるものの、本来の目的を果たしきれずにいる現状があるようです。
最後に
今回は日本のギャンブル事情について、その市場規模や公営ギャンブルに焦点を当てて見てきました。世界最大級のギャンブル大国である日本では、公共の機関に認められた公営ギャンブルだけでなく宝くじやパチンコなどがその市場規模を更に大きくしており、全ての合計をみると相当な金額でしたよね。ヒカキンさんのモノマネで人気のデカキンさんは3年連続で有馬記念の馬券を的中させている様子を見ると、夢がありますよね!
一方で、公営ギャンブルの多くは赤字に苦しんでいるという現実はあまり知られていないと思います。これを機に公営ギャンブルについて興味や理解を深めてみてはいかがですか。